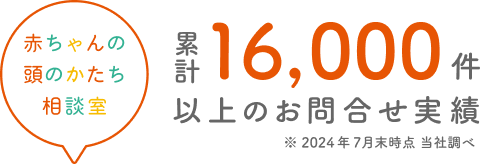赤ちゃんの頭のかたち相談室
Consult & Column
【医師監修】1ヶ月健診の内容|持ち物や注意点、費用について
生まれたばかりの赤ちゃんとの生活は大忙しです。
おむつ替え、授乳、寝かしつけ…慣れないお世話に試行錯誤する日々。
気づけば1ヶ月健診まで目前という方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、赤ちゃんとママが1ヶ月健診を安心して迎えることができるように、1ヶ月健診の内容や準備しておきたいことについてみていきましょう。
出産した医療機関で受ける場合は、赤ちゃんの1ヶ月乳幼児健診とママの産後健診を同時に受けることが多いようです。
もちろん、場合によっては赤ちゃんとママが別々のこともありますが、赤ちゃんやママが受ける一般的な1ヶ月健診の内容は決まっています。
本記事では、赤ちゃんとママの1ヶ月健診をわかりやすく解説していきますので、事前の準備に役立てていただくことができます。
1ヶ月健診の内容をあらかじめ知り、気持ちにゆとりをもって1ヶ月健診を迎えましょう。

吉田 丈俊 先生
1994年3月、富山医科薬科大学医学部卒業。1994年5月、富山大学附属病院小児科入局。1996年1月、大阪府立母子保健総合医療センター新生児科臨床実地修練生。1997年4月、厚生連高岡病院小児科(NICU専属)。2000年6月、京都大学ウィルス研究所情報高分子化学教室研究生。2002年4月、糸魚川総合病院、小児科医長。2002年10月、富山大学附属病院小児科助手。2004年10月ドイツリウマチ病研究センターベルリン、ポスドク。2007年10月、富山大学附属病院周産母子センタ−講師。2010年11月、富山大学附属病院周産母子センター、センター長、准教授。2017年10月、富山大学附属病院周産母子センター、特命教授。2022年4月、富山大学学術研究部医学系教授、兼富山大学附属病院周産母子センター長。現在に至る。
【資格】小児科専門医、 周産期専門医(新生児)、 臨床遺伝専門医
赤ちゃんの1ヶ月健診とは?
1ヶ月健診は生後1ヶ月の赤ちゃんを対象とした乳児健診です。
任意の乳児健診のため義務ではありませんが、ほとんどの赤ちゃんが受けています。
1ヶ月健診では、赤ちゃんの発育状況や栄養状態、からだの異常がないかを確認します。
また、赤ちゃんの健康状態や、育児の悩み、心配事に関して相談できる場でもあります。
いつ・どこで受けるの?
赤ちゃんの生後1ヶ月頃に、出産した医療機関で受けることが多いでしょう。
ママの産後健診にあわせて赤ちゃんも受けることができます。
この場合は、すでに医療機関から案内をされている方もいるのではないでしょうか。
里帰り出産などで1ヶ月健診を前に自宅に戻った場合、出産した医療機関で受けることができないことも。
健診を受ける医療機関が決まっていなければ、事前に医療機関を見つける必要があります。
たとえば、赤ちゃんは自宅近くで今後お世話になる小児科、ママは妊婦健診で通っていた医療機関などが問い合わせ先として考えられます。
問い合わせるべき医療機関がわからない場合は、お住まいの自治体へ相談するとよいでしょう。
費用はいくらかかる?
健診先の医療機関や自治体によって異なりますので、まずは健診を予定している医療機関やお住まいの自治体へ確認しましょう。
そもそも医療機関や自治体で負担する額が異なるのはなぜでしょうか。
1ヶ月健診は、保険診療の適応外とされる自由診療です。
自由診療は医療機関ごとに料金を設定するため、健診費用が異なります。
また、赤ちゃんの1ヶ月健診は義務ではありません。
任意の乳児検診の場合は助成の対象とならないため、自己負担となるのです。
赤ちゃんの健診費用は自己負担なしから1万円程度と大きく開きがあり、3,000~5,000円に設定している医療機関が多いようです。
ママの産後健診については、自治体が助成を行っており、5,000円を上限としている自治体が多い傾向です。
請求額が助成した額を超えた場合は自己負担となります。
ただし、医療機関によっては赤ちゃんの1ヶ月健診を無料で行っていたり、自治体によっては助成対象としていたりする場合もあります。
いずれにしても事前の確認が大切です。
1ヶ月健診の内容
ママの身体と心の回復状態、赤ちゃんの発育状態などを確認します。
ここでは、1ヶ月健診でママと赤ちゃんに対して確認される項目を確認していきましょう。
1ヶ月健診では悩みや気になることを相談できます。
相談したい内容は事前にまとめておきましょう。
赤ちゃんの症状で気になること(例えば湿疹、便の色など)はスマートフォンで写真で撮影しておき健診の当日に担当医の先生に見てもらうといいかもしれません。
チェック項目(ママ)
ママの健診では、母体の回復状態や、母乳はしっかりと出ているのかなどをチェックします。
また、産後はホルモンバランスが乱れたり、環境の変化からこころにも不調が起こりやすい時期です。ママはしっかりと身体・こころの状態を確認してもらいましょう。
一般的な健診項目は以下の通りです。
- 問診(生活環境,授乳状況,育児不安,精神疾患の既往歴,服薬歴など)
- 診察(子宮復古状況,悪露,乳房の状態など)
- 体重・血圧測定
- 尿検査(たんぱく・糖)
- エジンバラ産後うつ病質問票
チェック項目(赤ちゃん)
赤ちゃんの健診では、栄養や発育状態、運動機能の発達を確認します。赤ちゃんに関する心配事などを相談することもできます。
一般的な健診項目は以下の通りです。
- 身体発育状況(身長、体重、胸囲、頭囲)
- 栄養状態(栄養法、母乳などの飲み具合)
- 身体の異常の早期発見(黄疸、斜頸、内臓の異常、心雑音、股関節脱臼、頭部チェック、モロー反射ほか反射反応)
- こどもの健康状態や育児の相談等
健診の持ち物、服装
健診時に必要となる持ち物をご紹介します。
健康保険証や乳児医療証は持参しておきましょう。
1ヶ月健診は保健適応外のため必要ありませんが、健診結果によっては保険診療を必要とすることがあります。
赤ちゃんの健康保険証・乳児医療証の作成が間に合っていない場合は病院へ伝えましょう。
後日、保険診療分を精算することができますのでご安心ください。
|
赤ちゃんとママの服装
診察を受けるので着脱が簡単な服装がおすすめです。赤ちゃんとママにおすすめの服装をみていきましょう。
〈赤ちゃんの服装〉
脱ぎ着させやすい前開きの肌着やベビー服がよいでしょう。また、おくるみは温度調節や寝てしまった時にかけることができるので便利です。
- 前あきの肌着+前あきベビー服
- おくるみ(バスタオルで代用できます)
産後健診では子宮の内診や母乳の状態などの診察がおこなわれます。
スカートや脱ぎ着しやすいズボン、前あきのシャツなどがよいでしょう。
- スカート、ズボン(着脱が楽なもの)
- 前あきのシャツ
当日の赤ちゃん・ママの移動方法
赤ちゃんとママの移動は「抱っこひも」や「ベビーカー」が便利です。交通手段や病院の広さなどによって使いわけるとよいでしょう。ベビーカーは赤ちゃんを寝かせたまま移動できますのでママの負担は少ないですが、交通機関を利用する場合は乗り降りに負担を感じてしまうかもしれません。
抱っこひもでの移動はママの負担はありますが、交通機関を利用する場合の乗り降りにも、病院で赤ちゃんをあやす時にも便利でしょう。
【Q&A】1ヶ月健診でよくある質問
ここでは1ヶ月健診でママやパパから聞かれることの多い項目について説明します。
1ヶ月健診に行かなかったらどうなりますか?
1ヶ月健診に行かなかった場合は、病院が状況確認のために電話をしたり、必要に応じて役所の職員が訪問をすることがあります。
出生した病院を退院後、他の病院に長期入院していて健診に行けないなどの場合は、その旨を伝えてください。
里帰り出産なのですがどこで受けたらいいですか?
1ヶ月健診前に自宅に戻る場合は、出生した病院以外でも受けられることがあります。事前に病院に問い合わせてみるとよいでしょう。
湿疹やおむつかぶれが治りません
新生児の皮膚はとても敏感で、ホルモンの分泌が多く、おむつの蒸れや乾燥で皮膚のトラブルを起こしやすいです。不織布のお尻ふきが肌に合わない場合は、濡らしたコットンやガーゼで洗い流すようにお尻を拭くと改善されることがあります。
また、沐浴時に目の周りや脇の下、首、手足のシワに石鹸の洗い残しがあると湿疹ができやすいので、シャワーを使ってしっかりと洗い流します。
以前は新生児には保湿剤が必要がないと言われていたこともありますが、最近は新生児期からローションやオイルで全身を保湿をすることが推奨されています。
1ヶ月健診に保険証は必要ですか?
保健適応外の健診には必要ありませんが、健診結果によっては診療が必要になるため、持参しておくとよいでしょう。保険証の作成が間に合っていない場合は、病院からの指示を受けてください。
完全ミルク育児だと指摘されますか?
健診ではあくまでも赤ちゃんの健康を確認しているため、母乳かミルクを飲ませて体重が順調に増えていることが大切です。
完全ミルクだからといって、怒られたり、責められたりすることはないので安心してくださいね。
ミルクの吐き戻しが多いです
赤ちゃんは、からだに対して胃の割合が高く、吐きやすいものです。吐いても赤ちゃんの様子に変わりがなければ問題ないので安心してくださいね。
体重が増えない、母乳やミルクを飲みたがらない、といった場合は1ヶ月健診で相談しましょう。
母乳が足りているのか不安です
母乳が足りているのかの目安は、体重の増加とおしっこの回数と言われています。
体重は生後3ヶ月までは1日約25〜30g程度、1ヶ月で700g〜1kg程度増加していて、おしっこは1日8回前後出ていれば、水分は足りているようです。
気になる場合は、哺乳量測定といって、授乳の前後に赤ちゃんの体重を測り、差し引きから摂取した母乳量を計算する方法もあります。
鼻詰まりがなかなか治りません
赤ちゃんは鼻の奥が狭いので、鼻が詰まってブヒブヒ、フガフガという音がよくしています。必ずしも風邪をひいている訳ではありません。
普段と変わりなく、母乳やミルクが飲めていれば、問題ないので安心してくださいね。成長して鼻の奥が広くなってくれば詰まらなくなるでしょう。
寄り目になっている気がします
赤ちゃんは、目の周りの筋肉や視力が低いため目の位置が安定せず、寄り目に見えることがあります。成長と共に治るので安心してくださいね。
矯正が必要な寄り目に関しては、関連記事で解説しています。
頭がゆがんでいる気がします
赤ちゃんの頭は、産道を通るためにとてもやわらかく、少しの圧力でゆがんでしまうことがあります。主な原因は、出産前後の圧迫や向き癖ですが、まれに頭蓋骨が変形する病気が隠れていることもあります。
1ヶ月健診で頭のゆがみを相談することもできますが、担当の医師は頭のかたちに関して診察した経験が少ないかもしれません。ゆがみが気になる方は、「頭のかたち外来」で相談することをおすすめします。
頭のかたちのゆがみはチェック項目に含まれない
生後1ヶ月の赤ちゃんの親御さんからよくいただくお声に「頭がゆがんでいる気がするのですが、放っておいて大丈夫ですか?」といった不安があります。
実は、乳児健診で赤ちゃんの頭のかたちについて診察する項目は特にありません(2023年12月現在)。
頭部の診察では、頭囲の測定により病気の可能性を判別したり、大泉門(※)の閉じ具合を確認することがありますが、頭のゆがみについては、医師から特に指摘をしないことがほとんどのようです。
保護者から心配事を伝えても「気にしなくて良い」と返答されることが多いという意見もありました。
また、3,4ヶ月健診まで様子をみたり、家で寝かせ方を工夫するよう言われたりすることもあるようです。
しかし、ゆがみが大きい場合には寝かせ方では改善されず、ヘルメット治療が必要な場合があります。
ヘルメット治療は生後2〜6ヶ月には開始していることが望ましいとされているため、診察予約やヘルメット作成時間を考えると、次の健診まで様子を見ることは好ましくないかもしれません。
赤ちゃんの頭のかたちが少しでも気になる場合は、どの程度のゆがみなのか、どんな対処をしたら良いかなど、現在の状態を専門機関に相談してみることをおすすめします。
※大泉門とは赤ちゃんの頭部の骨の継ぎ目のこと。出産時に産道を通るため柔らかくなっているものが、通常1年〜2年程で閉じていきます。
もし頭のゆがみが気になったら
もし頭のゆがみが気になったら、「日常的にできる予防方法」と「医療機関で受けることができるヘルメット治療」の両方を知っておきましょう。
生後1ヶ月頃の赤ちゃんの頭はやわらかいので、向き癖などによっては、さらにゆがみが強くなってしまうこともあります。
そのため、赤ちゃんの向き癖をチェックし、同じ方向ばかりを向いて寝かせないように気をつけてあげましょう。
ゆがみの予防は手軽に始めることができますが、頭のゆがみが改善されない場合もあります。
その場合はヘルメット治療を検討しましょう。
ヘルメット治療を受けるには「小児科(赤ちゃんの頭のかたち外来)」を受診します。
小児科(赤ちゃんの頭のかたち外来)では、
赤ちゃんの頭のかたちのゆがみを測定し、必要に応じてオーダーメイドの矯正用ヘルメットを作成することができます。
赤ちゃんの頭の骨がやわらかい生後3~6ヶ月頃に開始することが推奨されているため、1ヶ月健診の際に気になったママは、相談もかねて医療機関に足を運ぶとよいでしょう。
まとめ|1ヶ月健診の内容や持ち物を知り、安心して当日をむかえよう
1ヶ月健診は出産した病院で受けることが多く、赤ちゃんが元気に育っているか、何か異常はないか、また、ママの回復状態、困っていることなどを確認します。
健診の当日は赤ちゃんとの移動やお世話など、ママひとりで慣れない場面に直面し、心細くなることもあるでしょう。
少しでも心配を減らすことができるよう、事前に当日を想定して服装や持ち物の準備をしておくことをおすすめします。
【記事の4つのポイントをおさらい】
- 赤ちゃんとの移動手段は抱っこひもかベビーカーがおすすめ。病院までの交通手段を考慮して移動手段を選択しましょう。
- 着脱しやすい服装で健診を受けましょう。
- 赤ちゃんやママのことで相談したいことは事前に準備。メモを持参するとよいかもしれません。
- 頭のゆがみは1ヶ月健診の確認項目にありません。あたまのゆがみが気になる場合は「赤ちゃんの頭のかたち外来」を検討してみましょう。
赤ちゃんとの慣れない生活の中で、ママは多くの不安や悩みを抱えてしまうものです。
1ヶ月健診は、日ごろ感じている不安や悩みを、医師や看護師、助産師などに相談できる機会ですので、赤ちゃんの成長を見守るとともに、ママ自身の不安を解消する目的でも活用してください。
まずは無料で相談してみませんか?

お電話でのご相談
0120-627-430《受付時間》 平日9時~17時
平日9時~17時