赤ちゃんの頭のかたち相談室
Consult & Column
【医師監修】長頭症とは?頭が縦に長くなる原因や特徴、対策方法について
更新日:2025年06月17日
「我が子の頭を横から見たら、なんとなく長い気がする…。」それは、もしかすると「長頭症」と呼ばれる頭のかたちのゆがみかもしれません。
赤ちゃんの頭のかたちのゆがみは、これまで「放っておけば自然に治るよ」「様子を見よう」という声が多く聞かれてきましたが、最近は積極的に治療を行うようになりつつあります。
生まれたばかりの赤ちゃんの頭はやわらかくて変形しやすいため、早期に対策をすれば頭のかたちのゆがみを予防できたり、改善を目指せます。
その一方で、場合によっては早急に治療が必要なケースもあります。
そこで本記事では、長頭症の特徴や原因、知っておきたいリスクや対策について解説します。
まずはお気軽にご相談ください
「赤ちゃんの頭のかたち相談室窓口」では、赤ちゃんの頭のかたちにお悩みの保護者さまから相談を受け付けています。 相談室スタッフが頭のかたちについてのお悩みをお聞きし、頭がゆがむ原因や、日常的にできる予防方法をお伝えしています。 不安なお気持ちやもっと知りたいことなど、ぜひお気軽にご連絡ください。 どなたさまでもWebフォームから無料でご相談可能です。
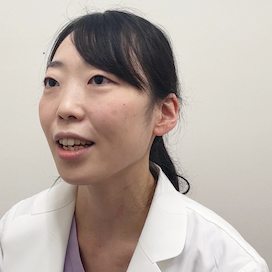
2013年、帝京大学医学部卒業、自治医科大学附属さいたま医療センターで初期臨床研修を終了後、2015年、同センター小児科に入局。同センター、自治医科大学とちぎ子ども医療センターで小児科専攻医として研修。2019年〜周産期科新生児部門 病院助教。2019年〜2020年、聖霊浜松病院 新生児科で専門研修を経て2021年周産期新生児専門医取得。2021年10月から自治医科大学附属さいたま医療センター 乳児頭のかたち外来開設から頭蓋変形の診療に携わり、現在に至る。
長頭症とは?

長頭症(ちょうとうしょう)は頭のかたちの一種で、頭の前後幅が横幅に比べて異常に長くなっている状態を指します。
イメージとしては、ラグビーボールのようなシルエットです。
長頭症は新生児~生後3カ月未満ごろまでに発生することが多く、子どもによって程度が異なります。軽度である場合には、自然に改善されることもある症状ですが、放置するとことで悪化するケースもあるため要注意です。また、長頭症を放置した結果、頭のかたちがゆがんだまま大人になることもあります。
長頭症の診断基準と測定方法
長頭症は、真上から頭を見た際に、明らかに前後に長くなっている状態である場合に診断されます。また、頭の横幅を参考にして、明らかに前後の方が長い場合や、正面から見た際に頭のてっぺん部分が高く伸びている場合などにも長頭症と診断されます。
新生児の頭のかたちを測定する際には、3Dスキャンを使うことがあります。3Dスキャンは、目で見てわかりやすく、正確な数値を計測できる優れたマシンです。
また、「クラニオメーター」といわれる測定器を使用するクリニックもあります。クラニオメーターは、物作りでよく使われるノギスに似た測定器で、赤ちゃんの頭に当てることでゆがみの程度を計測できる道具です。
これらのマシンや道具を複数組み合わせて、新生児の頭のかたちを計測するのが一般的。具体的なデータをもとに、長頭症の重症度を判断していきます。
発達への影響
長頭症は基本的には病気ではありませんが、場合によっては視力や歯のかみ合わせに影響を及ぼします。また、成長した際にコンプレックスに感じる場合もあるでしょう。
病気ではない長頭症は、位置的頭蓋変形に分類され、主に外的な圧力によって起こる変形です。まだ頭蓋骨がやわらかい新生児の時期になりやすいとされています。
寝返りを始める生後4カ月頃からは、赤ちゃん自身で頭を持ち上げられるようになるため、長時間にわたって同じ向きから圧力がかかるシーンが減り、頭のかたちが整いやすくなる時期です。赤ちゃんがより活発に動けるようになる生後8カ月以降からは、寝ている時間が徐々に減り、頭もバランスが整ってきます。
赤ちゃんの長頭症の原因は?
赤ちゃんが長頭症になってしまう原因は、主に3つあります。
横を向いて寝る癖がついている
長頭症になりやすい原因のひとつが、赤ちゃんの寝かせ方です。
長頭症になってしまう赤ちゃんの多くは、長い時間横向きで寝ている傾向にあります。
生まれて数ヶ月の間、赤ちゃんの頭蓋骨はとてもやわらかく、一定方向に圧力がかかり続けることで容易に変形してしまいます。
そのため、横向きで寝ているとその部分が平らになり、頭が細長くなってしまうのです。
例えば、NICU(新生児集中治療室)で長期間治療を受けている赤ちゃんは、長頭症になりやすいといえます。
これは、NICUでの処置の関係で横向きに寝かされていることが多いためです。
出産時に逆子や吸引分娩だった
母親の子宮の中や、出産時の環境によっても長頭症となる場合があります。
とくに逆子の赤ちゃんは、頭が伸びたような状態で出てくることが多く、長頭症になりやすいとされています。
吸引分娩の場合も、赤ちゃんの頭に吸着カップを付けて引き出すため長頭症になりやすいと考えられます。
頭蓋骨が変形する病気
稀にではありますが、病気が原因となっている場合もあります。
頭蓋骨のつなぎ目が何らかの原因で早くつながってしまう頭蓋骨縫合早期癒合症(ずがいこつほうごうそうきゆごうしょう)という病気です。
この病気の場合は、頭蓋骨のつなぎ目が通常よりも早くにくっついてしまい骨の成長が阻害されるため、頭蓋骨が変形してしまいます。
長頭症は、この頭蓋骨縫合早期癒合症の一種の、矢状縫合早期癒合症(しじょうほうごうそうきゆごうしょう)で現れる頭のかたちに似ているのです。
頭蓋骨が部分的にくっついていると、脳の成長に合わせて頭蓋骨が正常に拡大していくことができません。
それにより、成長すべき脳の発達が阻害されてしまう可能性があり、場合によっては早急に治療が必要なケースもあります。
長頭症は自然に治る?知っておきたいリスクについて
赤ちゃんの頭のゆがみに対して、「自然に治るよ」や「赤ちゃんの頭のかたちはよく変わるものだよ」と言われることもあるかもしれません。
しかし、頭のゆがみをそのままにしていると、次のようなリスクにつながる可能性があります。
▼【医師監修】赤ちゃんの頭のかたちを綺麗にするには?対策や注意点を紹介
頭のかたちがゆがんだままになってしまう
赤ちゃんの頭蓋骨は、生後まもなくはとてもやわらかく、かたちが変わりやすいのですが、成長するにつれて硬くなり、かたちが定まってきます。
次第に気にならない程度に改善するケースもありますが、重症度によっては、ゆがみをそのままにしておくと、頭はゆがんだかたちのままで硬くなってしまうことがあります。
赤ちゃんの頃は気にならなくても、頭のかたちが原因で好きな髪型にできなかったり、かぶりたい帽子が合わなかったり、といったことが起こる可能性もあります。
発達に影響が出てしまう可能性も
寝かせ方や出産前後の環境による頭の歪みの場合は、基本的に脳の成長や発達には影響しないと考えられています。
矢状縫合早期癒合症が原因となっている場合は、頭蓋骨のつなぎ目が早期にくっついてしまうので、その部分では脳の成長に合わせて頭蓋骨が成長していきません。
赤ちゃんの脳は生まれてから約6ヶ月で2倍もの大きさに成長しますが、矢状縫合早期癒合症によって脳の成長が妨げられる可能性があります。
脳の成長が妨げられることによって、運動発達や成長発達に影響が出る可能性も否定できません。
長頭症の治療法
ここからは、長頭症の具体的な治療法についてチェックしていきましょう。
ヘルメット治療の効果と装着方法
ヘルメット治療は、専門のクリニックで受けられる頭の形かたちを整えるための治療法です。もちろん、長頭症の場合にも活用されます。ヘルメット治療は、矯正用ヘルメットをかぶることで赤ちゃんのやわらかい頭を保護しつつ、すでに変形して平らになってしまった部分の成長を促し、自然な頭のかたちへと近づけていくものです。
赤ちゃんの体に負担のないよう、生後2~3カ月ごろから開始するのがスタンダード。また、頭蓋骨がやわらかい生後6カ月頃までにヘルメット治療を開始すると、効果が得られやすいとされています。
日本の矯正用ヘルメットは、個々の赤ちゃんの頭のかたちに合わせてオーダーメイドで作成します。一般的なヘルメットと同様に、頭にかぶるだけで治療が可能です。
最初は数時間からヘルメットの着用を始め、経過を見ながら着用時間を長くしていくのが基本的な治療の流れです。最終的には、お風呂の時間を除き、寝ている間もずっとヘルメットを着用します。
ヘルメット治療の期間は、約6カ月間程度です。
手術が必要なケース
外的な要因が関係している長頭症を治療する場合には、ヘルメット治療などが一般的ですが、何らかの病気によって赤ちゃんの頭のかたちが前後に長くなっている場合には、手術が必要なケースがあります。
頭蓋骨縫合早期癒合症の場合、手術によって正常な頭蓋骨に近いかたちに組みなおす方法が一般的です。また、骨延長器を使った手術や、内視鏡を使って骨切りをおこない、その後ヘルメット治療をおこなうこともあります。
成長に応じた治療の見通し
赤ちゃんの時期は、脳や頭蓋骨を含む、体全体が急激に成長します。そのため、ヘルメットなどで頭のゆがみを治療する場合にも、個々の成長に合わせて治療を進める必要があります。
定期的に病院に通い、医師のアドバイスのもと、成長にマッチした治療をおこないましょう。医療機関に行くことで、具体的な治療方法の提案をはじめ、今後の治療の流れや見通し、日常生活におけるアドバイスもしてもらえます。
新生児の頭が長い場合の対処法
ここからは、新生児の頭が長い場合に、実践したい対策法をご紹介していきます。ちょっとした工夫でゆがみが軽減されることもあるため、できることから試してみてください。ただし、確定診断のためには病院を受診する必要があります。
日常生活で気をつけること
頭の一部分だけに集中して圧力が加わらないよう、同じ向きで寝かせ続けないことが大切です。新生児の時期から首が座るまでの間に、タミータイムを積極的に取り入れてみましょう。
タミータイムとは、赤ちゃんがしっかり起きているタイミングで、大人が見守りながらうつぶせで過ごす時間のことをいいます。「うつ伏せ遊び」「腹ばい練習」などといわれることもあり、乳幼児突然死症候群や頭のゆがみ予防としても効果的です。
このタミータイムは、新生児の場合1回数分程度おこなうのが一般的です。はじめは、短い時間でトライし、慣れてきたら徐々に時間を長くします。1日合計10分程度を目安に取り入れてみましょう。タイミングとしては、お昼寝の後やお風呂上り、おむつを替えた後などがおすすめです。ミルクを飲んだ後などは、嘔吐する可能性があるため避けましょう。
慣れないうちは、パパやママのお腹の上などでおこない、慣れたらマットレスや畳といった硬かたすぎない場所で挑戦してみてください。また、赤ちゃんが嫌がったらすぐにやめるなど、無理のないペースで取り組むことも覚えておきたいポイントです。新生児は、まだ自身で首を持ち上げることができないため、窒息しないよう十分に配慮することも忘れてはいけません。大人が見守りながら取り組んでみてください。
赤ちゃんの頭の向きを工夫する方法
長頭症は、横向きに寝ている時間が長い場合に、頭の側面に圧力がかかることが影響している場合があります。そのため、授乳や抱っこのたびに頭の向きを変えたり、寝ているときに赤ちゃんの頭から背中あたりにかけて、ぐるぐると巻いたタオルを挟んで頭の向きを調整したりする方法があります。ただし、タオルで赤ちゃんの向きを変えるのは、万が一の事故を避けるため夜間は控えましょう。
多くの場合、赤ちゃんの向き癖によって、長時間同じ方向を向いてしまいがちなので、パパやママが意識的にサポートしてあげることが大切です。赤ちゃん自身の頭の向きをタオルなどで調整する他、パパやママが話かける方向を工夫してみるのも良いでしょう。
まずは、赤ちゃんの向き癖をチェックするために、普段の動きを観察してみてください。
専門家によるアドバイス
新生児の頭が長く、気になる場合には小児科などの医療機関を受診するのもひとつの手段です。
「ちょっと長い気がする…」程度でも、気軽に相談に行ってみてください。早期治療を始めることで、スムーズに頭のゆがみを整えることができるかもしれません。
「長頭症かも」と思ったらどうすればいい?
赤ちゃんの頭のかたちが気になったら、まずはご家庭で簡単な対策を行ってみましょう。
赤ちゃんの頭のかたちを自然な状態で保ち、一定方向に圧力がかかり続けないように注意してあげるだけでも、十分な対策の一つです。
頭のかたちがやわらかいうちに対策する
頭のかたちのゆがみは、頭蓋骨がやわらかいうちに対策をとることが重要です。
ご家庭でも、長時間同じ方向で寝かせないようにする、授乳時や抱っこの際もタオルや枕を上手に使って赤ちゃんの姿勢をサポートしてあげるなど、体位変換を行うことでゆがみの予防・改善につながります。
例えば、横向きで寝る癖がついていたら、バスタオルを使って向き癖を治す方法があります。
赤ちゃんを寝かせるとき、折りたたんでぐるぐる巻きにしたバスタオルを、赤ちゃんを向かせたい方向と反対側の背中から体の下へ入れ込み、赤ちゃんの寝る向きを支えてあげることで向き癖を修正します。
ただし、赤ちゃんに過度な負担がかからないよう、2時間程度を目安に姿勢を変えてあげるようにしましょう。
医療機関へ相談する
できる対策を取りつつ、それでも赤ちゃんの頭のかたちが気になると思ったら、まずは医療機関や専門医に相談することをおすすめします。
医療機関できちんと検査を受けることで、頭のゆがみの原因や対策についてのアドバイスや、必要に応じた治療を受けることができます。
医療機関では、頭のゆがみの原因が病気によるものなのか、外部からの圧力によるものかを診断してもらうことができます。
頭のゆがみの原因が頭蓋骨縫合早期癒合症だった場合、さまざまな部位に影響が及ぶことから早期の治療が必要となり、手術は変形が広範囲に広がる前の1歳以下の段階でおこなわれます。
頭のゆがみの原因が病気であっても、外部からの圧力によるものであっても、赤ちゃんの頭蓋骨がやわらかいうちに対策・治療を始めることが重要です。
また、頭のゆがみを診てくれる医療機関では、ゆがみの程度や赤ちゃんの頭の成長にあわせてアドバイスをもらうことができます。
頭のゆがみはヘルメット治療も検討してみましょう
ヘルメット治療は、矯正用ヘルメットをかぶることでやわらかい頭を保護しつつ、すでに変形して平らになってしまった部分の成長を促し、自然な頭のかたちへと近づけていくものです。
赤ちゃんの頭蓋骨がやわらかい生後6ヶ月頃までにヘルメット治療を開始すると、効果が得られやすいとされています。
このヘルメット治療に用いる矯正用ヘルメットは、個々の赤ちゃんの頭のかたちに合わせてオーダーメイドで作成します。
最初は数時間からヘルメットの着用を始め、経過を見ながら着用時間を長くしていき、最終的にはお風呂の時間を除き寝ている間もずっとヘルメットを着用します。
ヘルメット治療の期間は、約6ヶ月間程度です。
また、現時点の日本におけるヘルメット治療は保険適応外であるため、どうしても治療にかかる必要は高くなってしまいます。
医療機関や使用するヘルメットのメーカーなどでも異なりますが、ヘルメット治療の総額は約40~60万円(税込)です。
まとめ|長頭症かも?と思ったら早めに相談しよう
長頭症は「自然に治る」ものではなく、場合によっては適切な治療が必要です。
矢状縫合早期癒合症という病気によって長頭症となっている場合もありますし、外部からの圧力が原因となっている場合も、早めに対策をとることが重要です。
赤ちゃんの頭のかたちに少しでも不安を感じたら、早めに頭のゆがみを診てくれる医療機関に相談してください。
先生に相談してみませんか?
「赤ちゃんの頭のかたち相談室窓口」では、赤ちゃんの頭のかたちにお悩みの保護者さまに向けて、無料相談を受け付けています。
- うちの子にヘルメット治療は必要だろうか?
- 費用はどれくらいかかるの?
- かかりつけ医師には「大丈夫」と言われているけど?
まずは相談室スタッフが頭のかたちについてのお悩みをお聞きします。 ご希望があれば病院や医療機関も紹介していますので、不安なお気持ちやもっと知りたいことなど、ぜひお気軽にご連絡ください。

お電話でのご相談
0120-627-430《受付時間》 平日9時~17時
平日9時~17時
Webからは24時間ご相談受付中
関連記事
others
- 頭のゆがみ
【医師監修】赤ちゃんの頭のかたちを綺麗にするには?対策や注意点を紹介
監修:草川 功 先生

- 頭のゆがみ
新生児の向き癖をタオルで改善!やり方やタオル選びのポイントを解説

- 頭のゆがみ
【医師監修】吸引分娩で頭のかたちが戻らないって本当?頭蓋変形の原因や対策を解説
監修:日下 康子 先生

- 頭のゆがみ
【医師監修】絶壁は治る?頭の形の変形対策、予防、治療方法を紹介
監修:楠田 聡 先生

- 頭のゆがみ
【医師監修】斜頭症とは?頭がゆがむ原因や放置リスク、予防・治療方法について
監修:江藤 宏美 先生

- 頭のゆがみ
【医師監修】赤ちゃんの絶壁の治し方は?原因や自宅でできる予防や対処法を解説
監修:草川 功 先生